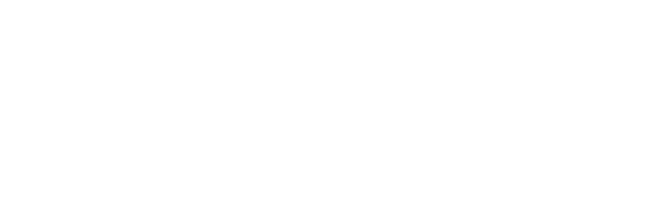日本文化・着物文化に触れる興味深い本2冊紹介します。
着物に関する本・興味深い本のご紹介です。
今着物に関する本、2種類読んでいます。
すでに読んだ人、読んでいる人もいらっしゃるかと思いますが。
1. 『あきない世傳 金と銀』高田郁(かおる)著 ハルキ文庫 文庫本
2. 『銀太郎さん お頼み申す』東村アキコ著 集英社 漫画
1.の場合、旅行に出かけるので、飛行機の中の時間潰しにと図書館に頼んでいたのが間に合わなく、帰ってきたら図書館に届いていた、ということで読み始める。
テレビでも(NHKBS)でも小芝風花ちゃん主演で放映されていて、呉服屋さんの話だなという程度に興味はあった。
読み始めたら止まらない。寝食忘れて、という言葉が久しぶりに蘇ってきた本でした。
表現のほとんどに、情景を表すのにその時代、江戸時代の言葉が使われている。
例えば『色』の表現にも今では「日本の色」という専門書を開いて確認する名前が次から次へと出てくる。
《着物の三大特徴》として講義をする中で、その一つ、日本の色・模様を挙げて説明しているのですが、こんなに日常的な場面で具体的な色として表現されていることに、胸の中があったかくなっていくのを覚え、さらに先を読みたい、となっていくのです。
【日本の色の特徴】としてレクチャーする時にお伝えするのは
色数の多さ・・四十八茶百鼠 と言われているように、茶系統の色だけで48通り以上。鼠色に至っては100種類以上にもなるのです。
しかし考えてみれば、パレットの上で色を混ぜていくと、そのグラデーションではいくらでも違った色が出せるのも事実です。
ではなぜ、日本の色が多いと言えるのか??
それは、その微妙に違う一つ一つの色に、それぞれに名前が付けられているのです。
そしてその名前は、今回この本の中に出ているような、日本の情景を映した名前になっているのです。
日本人の自然との一体感を感じるその感覚こそが、日本の四季のなかで長い時間をかけて育まれた、日本人ならではの感覚だと思います。
ですので、それらの言葉に接した時、日本人としての心の琴線に触れて、懐かしい豊かな気持ちになるのでした。
呉服屋というところで、絹物、木綿物(太物)のことも色々出てきて、着物に関心持っているものとして、勉強にもなり、また筋立ての面白さもありで、読むのが止まりません。
2.の漫画は、着物に興味の無いはずの娘が、こんな漫画読んでるから見るんだったら貸してあげる、と貸してくれた本。
漫画なので、あっという間に読み進める物だけど、着物について知らない人にはわかりやすいかな。そんな感じで、こちらも興味を持って読みました。
着物は好きだけど、あまり知らないという方、この2冊、ぜひ読んでください。
わからないことはわからないでも、こんなことが!と気づくだけでも読んでいただく価値があると思います。