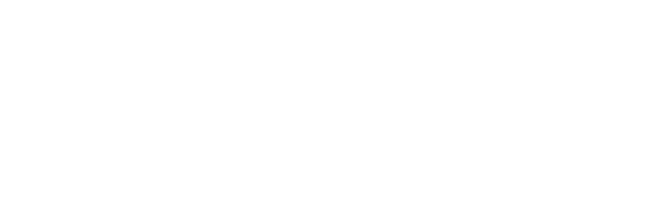七五三祝いに思う事
母が着た着物が子供へ、孫へ。
その成長を喜び祝う七五三の祝い儀に。
箪笥の中に眠っているお荷物着物! 終活・遺品整理・片付け、そして買い取り業者へと流れていく着物。
でも、七五三のお祝い着には、祖母から孫へ、母から子へと伝わっていく着物がある。
『蘇活継承』 蘇らせて、活用して、次世代へと継承していく。
そのこと自体が着物文化そのものなのです。

通過儀礼の一つである七五三のお祝いです。
10月の初めの頃から、11月下旬ごろまで続く、七五三のお祝いに伴って、出張着付けのご依頼が来ています。
土日は日に平均2件ほど、多い日は3件、早朝から午前中にあちこちを回る事になります。
お子様のこれまで無事に育ったことを祝い、更にこれからも幸せな成長が出来ますようにという願いを込めて祈願することです。
3歳:「髪置」の儀 髪の毛を伸ばし始める時 男の子・女の子
5歳:「袴着または着袴(ちゃっこ)」の儀 男の子 大人への第一歩として袴を着る儀式
7歳:「帯解」の儀(地域によっては紐解きともいわれます) 女の子が紐のみで着るのから帯を付ける様になる儀式
七五三の歴史
室町時代からあったという事ですが、広まっていったのは、江戸時代。
1681年に五代将軍が長男の健康を祈願したのが11月15日という事で、それを習って、武家や有力商人が七五三は
11月15日に行う習慣となりました。
江戸中期に呉服屋がこの3つの行事を商業政策に取り入れ、宣伝したことで流行していった一因でもあるようです。
明治時代になって、それが庶民にも普及していきました。
古来、伝染病や病気、怪我で子供が亡くなることも少なくなく、無事に成長して節目を迎えることが出来るのは、
親にとっては何よりの喜びであったでしょう。
また、七五三で神社に参拝するということは、神様の守護を祈ると同時に、地域からも社会人格を承認される
通過儀礼でもあるのです。
現代においても、子供が無事に育っていることに感謝し、一層の成長を願う親の気持ちは、変わることなく
七五三の晴れの日もお祝いとして受け継がれているのです。
現代にプラスして考えられるのは、子供の成長を見ていく過程にあって、その節目、節目での子供の様子を
晴れの日と合わせて、写真に残してあげる、という役割も大きくなっていることかもしれません。
着物を着るための準備
まずは、七五三のお祝いで着物を着よう!と思われたこと自体、素晴らしい事で、嬉しいですね。
お着物での お・も・て・な・し !!
お着物を着るという事は、洋服でのドレスアップと違って、普段考えていない中での高いハードルを越えて
そこにいらして頂いているのだと思います。
着物を着ること自体華やかで、晴れの日の演出には最高なのですけれども、
お子様に対しても、時には参列されているでしょう、おじい様、おばあ様にも
そしてお参りする神様にも お祝いをそのような最高の お気持ちでお祝いするのです、
というおもてなしの心なのです。
高いハードルの先には、最高で最大のおもてなしの心を届けることになるのです。